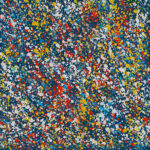Melancholia
Mar,13 2012 12:35
ラース·フォン·トリアー監督作品"メランコリア"を観に行ってきた。
いや、良かった。やはりラース·フォン·トリアーの作る映画は素晴らしい。
世界の終わりの時を映画にした今作であるが、観る人によって色んな解釈がある様子。
単純に地球滅亡の最後の日々的な解釈や、重度の鬱病患者スチールブレイカー叔母さんの妄想乙の世界系などなど…。
惑星衝突と云うSF的なところにスポットをあてるか、主役のキルスティン·ダンストの鬱にスポットをあてるか、はたまた、シャルロット·ゲンズブールとの姉妹としてスポットをあてるかで、だいぶ物語の解釈が異なってくる。
当然の事だけれども、大前提として意図されているものの正確なところはラース·フォン·トリアー本人しか分からない訳ではある。
しかし、観る側がどう感じるかは勝手だと思うので、足りない頭を一晩振り絞って辿り着いた勝手な解釈を書き綴って行こうと思う。
結論から言うと、この作品は2人の対照的な姉妹それぞれが感じるメランコリー(憂鬱)の原因となるもの、忌み嫌い恐れているものを、それぞれの章にて表していると思われる。
極論を言えば、地球に迫った惑星メランコリアはあくまでメタファーに過ぎず、それが手に負えない程の巨大な憂鬱の原因としての表現ならば、別に地震でもなんでも良かったのではあった気はする。
が、あくまで物語の設定としての惑星なので、それはそれとしたい。
Opening
惑星衝突までの成り行きをハイパースローで、まるで絵画的に表現されている。
タイトルも出てないしあくまで序章って事なのであろうが、それにしては美し過ぎる上に"トリスタンとイゾルデ"と一体化して身震いする程。
DVDの方の"ダンサー·イン·ザ·ダーク" の最初とか "奇跡の海"の切り替わりの部分にもこんなのがあった気がするが、美しさのレベルが段違い。
第一部 『惑星を怖がらない妹』
第一部『ジャスティン』と銘打ったこの章はそのタイトル通り、妹キルスティン·ダンスト(以下、ジャスティン)の物語である。
先ずは、のっけのリムジンのシーンからいやらしいまでに小さい嫌な事が次々と発生し、蓄積させる事でフラストレーションを増大させるラース·フォン·トリアーの手法はお見事。
しかし、リムジンのシーンのジャスティンは、早く式場に行かなきゃいけない筈なのに何故だか楽しそう。
時間が経過して、式場に到着、自らの結婚式が大勢の人々の中で進んで行くにつれて、ジャスティンのメランコリーは高まっていく。
なぜなら、姉シャルロット·ゲンズブール(以下、クレア)が望む様なステキなあれこれと同じ価値観をジャスティンは持ち合わせていない。
自分縛る多くのもの、結婚、仕事、人間、普遍的なもの等々、それがジャスティンの憂鬱を増幅させ、その憂鬱から逃れるべく、ジャスティンの行動は常軌を逸していく。
つまりジャスティンは『惑星の衝突など怖くない』女なのであって、彼女が恐れているのは『自我を無くす』事なのである。
正直、第一部を観てジャスティンが多少アンニュイだとしても、それほど鬱病とは個人的にどうしても思えない。
惑星自体の扱いも小さく、しまいには姿を消してしまう。
ジャスティンの望む普遍的でないものは、彼女の意思に反して遠のいて『無くなって』しまうところで終わる。
彼女主体としての物語は第一部で完全に完結しているかと思われる。
第二部 『惑星を怖がる姉』
時間も違えば次元も違うと云うくらい状況は変化している。
ジャスティンの結婚がどうのとかは姉クレアの物語の中では問題ではないし、惑星の状況やらと総合して時間、次元的にも第一部のジャスティンとは完全に異なる設定の中でクレアの物語は進む。
第一部であれだけ場を締めていた人々は家族以外は誰も出てこない。
ここで先ず姉が孤独に対してある種の憂鬱を感じるのではないかと云う憶測をしてみる。
そして第一部から豹変した重度の鬱病の妹。姉は自我を持つ奔放な妹に対して『時々、あなたがすごく憎い』けれども、基本的には愛してもいる。
その強い自我を持った妹が重度の鬱病により失われる事への恐れ、憂鬱。
と、同時に彼女は凡庸な自分の理解を超えた事象に対しても強い憂鬱を覚える。
惑星明かりに照らされて真っ裸で寝そべっているような妹に対して理解しがたい感情になり、そして『時々、あなたがすごく憎い』くなる。
異常な程に接近する惑星メランコリア。
本当の事を伝えてくれない夫に対してのフラストレーションから、本当に事が起こった時に頼るべき夫のいない恐怖。
人間的過ぎる程、人間的な生活に守られていたクレアが、自分自身が息子や妹を守らなくなくてはいけない恐怖。
惑星メランコリアは異常な程に接近する。理解を超えている。
夫は既に亡く、妹も頼りにならない。
息子を抱えて、18番までしかない筈の19番コース、理解を超えた19番コースを恐怖の中を奔走する。
しかし、それも徒労に終わり、まるでこの惑星衝突と云うハプニングを待っていたかの様な冷静な妹の元に戻る。
姉の恐れは文字通り、『理解を超えたものによって全てを無くす』事であり、これは精神的なものを無くす恐怖を抱えた妹と対極であるとも云える。
妹の精神は映画の序盤と終盤は安定し、中盤はメタメタである。
それに引き換え、姉は映画の序盤に妹の事でやきもきし、中盤で均衡を保ち、終盤で崩壊する。
姉妹それぞれの精神状況の流れの対極をこれほど見事に表現するラース·フォン·トリアーの手腕。
そして惑星は接近し、クレアの望む普遍的なものは彼女の意思に反して全てを飲み込み、『無くなって』しまう。
…
…
…
うーん、凄くないか? まぁ、勝手な解釈だけれども。
黒髪と金髪って云う設定からして、"マルホランド·ドライブ"を思い出す。
今作はなんと云うか、ここ最近のラース·フォン·トリアー作品と"キングダム"の頃より前のラース·フォン·トリアー作品との良いところが合わさった様な気がする。
"奇跡の海"あたりから、 前作"アンチクライスト"まで、ヒロインいじめのラース·フォン·トリアーのドSっぷりが発揮されていた訳だけれども、今作では"キングダム"の時みたいな『神の目線』的な視点と、まぁ大きい意味でのヒロイン2人いじめとでうまく融合されている。
画面の色合いも第一部の暖色から第二部の寒色へとしっかり分けてあるし。映画全体のバランスがとても良い気がする。
まぁドグマ95の誓いが守られているかはどうかは微妙な感じはするけど。
そんなドSな筈のラース·フォン·トリアーが見せた優しさ、『魔法のシェルター』とは、自身や人々を不安から解放、防御するための『小さい嘘』。
ジャスティンが甥っ子と姉にみせる慈愛に満ちた嘘は、メランコリーの前では無力ではあるものの、束の間の安堵を得る。
そんな優しさをラース·フォン·トリアーはキルスティン·ダンストに託し、彼女もそれに答えたから見事なのだ…と勝手に思う。
何はともあれウド·キアーが出ているだけで、やっぱり落ち着くラース·フォン·トリアー作品、傑作。
いつ超新星爆発するかと言われているペテルギウスに思いを馳せてみる今日この頃。
category: カルト
tags: ラース・フォン・トリアー