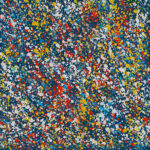The Seventh Continentと人間
Sep,09 2010 14:00
先日、レンタル落ちの「裸の島」('60)を入手。
ちょいちょい訪れる新藤兼人作品への渇望が再燃したので、「人間」('62)を観る。
簡単に説明すると極限状態に陥った人間が何をやらかすかと云った映画なのですが、いやはや浅ましい。
先日亡くなった佐藤慶の役どころが浅まし過ぎる。
けれども気持ちはよーく分かる。やっぱり自分が一番大事なんだな、人間ってのは。
「罪と罰(新潮文庫)」の中にこんな一説がある、
"ある死刑囚が、死の一時間前に、どこか高い絶壁の上で、しかも二本の足をおくのがやっとのような狭い場所で、生きなければならないとしたらどうだろう、と語ったか考えたかしたという話だ、ーまわりは深淵、大洋、永遠の闇、永遠の孤独、そして永遠の嵐、ーそしてその猫の額ほどの土地に立ったまま、生涯を送る、いや千年も万年も、永遠に立ちつづけていかなければならないとしたら、ーそれでもいま死ぬよりは、そうして生きていけるほうがましだ!生きていられさえすれば、生きたい、生きていたい!どんな生き方でもいい、ー生きてさえいられたら!・・・・なんという真実だろう!これこそ、たしかに真実の叫びだ!人間なんて卑劣なものさ!その男をそのために卑劣漢よばわりするやつだって、やっぱり卑劣漢なのだ"
と己の理屈から殺人を犯したラスコーリニコフは言う。
と云う訳で、極限に追い込まれると生き抜く為に弱肉強食となるのは生きものの性なのだろう。
そんな恐怖なお話を見事な撮影で表現されている。
甲板から細く漏れ出る灼熱の太陽光で照らされてうかがえる狂気に変貌していく人間が何とも強烈。
と云うか乙羽信子が笑えるほど体張り過ぎ。だから好きなんだけど。
ひたすら理性を守り通し、生を渇望し続け独り生き残る。
殿山泰司もまた証言もなんにもないのだから人肉喰らいの汚名を着せられ後ろ指をさされ続ける人生を歩みかねないと云うなんとも残酷な結末。
欲と理性の2つの側面がせめぎあい理性が生き残ったって映画なのだけれども、人生って複雑なものである。
"その男をそのために卑劣漢よばわりするやつだって、やっぱり卑劣漢なのだ"と云う一説がズシーンと重くのしかかる。
外は台風だったので、微妙な臨場感と共に鑑賞しました。
で、2本目はミヒャエル・ハネケ監督の映画デビュー作品で "The Seventh Continent"('89)を観る。
ミヒャエル・ハネケ監督作品は"Funny Games"('97)しか観た事がなく、面白かったけれどもあまりにトラウマ過ぎていささか他の作品を観るのを敬遠していたのですが、今作もやっぱりトラウマ級だった。
実際にあったお話との事で、先進国ならどこでもみられるありふれた家庭が崩壊していく様を、'87、'88、'89年に渡り、プロットで淡々と語られていく。
それはもう淡々と。
生活のすべてが最後の1日に自分たちの手で破壊されゆく様もまた淡々としております。
家族は1つの終焉に向かいあまりに淡々と破壊し始めるので観ている方はこの人たち一体なにやってんのーって感じなのですが、
段々と良く分からない不安感と悲しみに支配されていきます。
そうしてまだ見ぬ第7の大陸へ行くのだそう。
重苦しい、実に重苦しい。ハネケ作品はやっぱり後味が重苦しい。がそれがまた嫌いではない。
"人間なんて卑劣なものさ!その男をそのために卑劣漢よばわりするやつだって、やっぱり卑劣漢なのだ" って一説がまたズシーンとくる。
とむやみに重いのを2本立て続けに見るのは良くないと結論。
笑える映画が観たくなってきた。
そんな今日この頃。